「時計台の鐘」という曲をご存知ですか?
皆さんは「時計台の鐘」という曲をご存知ですか?
大正12年にヴァイオリン演奏家で作曲家でもある
高階哲夫が作詞作曲した作品です。
彼が当時恋人であった声楽家・村井満寿子と
札幌に演奏旅行へ出かけた際の体験が元になっています。
しかしその演奏会は残念ながら不評に終わり、
新聞でも厳しい評判が掲載され
落ち込む高階を慰めようと、
満寿子や周囲の人々は月寒(つきさむ)の
羊ヶ丘に高階を案内します。

札幌の自然や、人々の温かさに触れた高階は、
東京に戻ってから、その記憶を元に
「時計台の鐘」を作曲しました。
「時計台の鐘」の音楽的構造
まず、伴奏をする際に使っている、
「日本抒情歌全集1」を
参考にして解説します。
- 拍子 :三拍子
- テンポ:Larghetto(ラルゲット)
ラルゴよりやや速く♩=63と記載されています - 調 :ニ長調(D major)、
明るく晴れやかなイメージを持つ調性です。
曲は2番までで構成されており、譜面はピアノ伴奏付きで見開き2ページです。
鐘の音を思わせるイントロ
まずイントロは、鐘の音を表している和音の響きです。
“ディンドン”というリズムでコードがなりますが、
まさにここが私の好きなところです。
特に不思議なのは、1小節目がD7の和音が入っている点です。
右手だけで聴くとF#dimで
1小節目からミステリアスな響きです。
D7は、本来ニ長調には含まれない
「C」の音が含まれており、
初見ではその違和感に驚かされます。
このコードには「不安定さ」や
「次へ進みたくなる」という
心理的効果があり、
聴き手の興味を引きつける狙いがあると考えられます。
そんなミステリアスななんとも言えない響きの
鐘の音が4小節あった後に…!
イントロも不思議だけど、歌の始まりも不思議!
さらに、歌の始まりも不思議なんです。
大体の曲は歌の始まりは、
その調の主和音(Ⅰ)から始まることが多いですが、
この「時計台の鐘」は
最初にBm(Ⅵm)から始まります。
「時計台の〜」Bmでどこか
切なさや情感がにじみ出して、
次に「鐘がな」で主和音のDに戻り
「る」でA7(Ⅴ7)へと展開していきます。
感情の流れとコード展開が
自然とリンクしています。
また、メロディは歌っていてとても気持ちよく、
後半に最高音が「綺麗な」のところでEまでありますが、
本当に綺麗なメロディなので納得。
その後オクターブ下のDまで落ちるのも
ドラマティックな見せ場になっています。
最後はフェルマータでたっぷりと伸ばして
テンポを落としながら「鐘が鳴る」と
噛み締めます。
ここの最後の和音は澄み切った主和音のDです。
迷いがなくなったかのようです。
歌詞について
さて、作詞もしている作曲者の高階は富山の出身で
学校も東京音楽学校なので
色々な資料を見ましたが
北海道には住んだことがないような印象を受けます。
しかし「時計台の鐘」の風景は、
まさに北海道・札幌の景色が丁寧に描かれています。
↓一番の歌詞に出てくるポプラ↓

本州にもポプラがあるそうですが、
やはり北海道の広大な景色の中で見る印象は違う気がします。
梢というのは「樹の先」という意味で、
朝の日の光が、樹の先に重なる様子を一番では歌っています。
↓2番の歌詞に出てくるアカシヤ↓

たとえば、札幌の百合が原公園には
ミモザアカシアがあります。(©︎写真AC)
まとめ
このように、「時計台の鐘」は、一見すると
明るく平和な抒情歌のように見えますが、
奥深いイントロやコード進行、
そして詩の内容からは、
哀愁や情緒を深く感じ取ることができます。
札幌での体験を通して、
切なさと明るさ、希望の色が入り混じったこの曲は、
単なる観光風景の描写ではなく、
高階哲夫自身の心の旅を映しているようにも思えます。
鐘の音に耳を澄ませるとき、
あなたはどんな風景を思い浮かべるでしょうか。



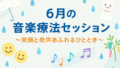
コメント